市町村合併に「NO」と言えますか? (下)地域メディア研究所代表 梶田博昭 |
|
(社団法人北海道開発問題研究調査会機関誌「しゃりばり」2001年9月号に掲載した記事を補筆再録) |
■タカをくくるか、腹を括るか さて、北海道ではどうか。合併に向けた具体的な動きとしては、釧路市と釧路町がやや先行し、留萌管内や空知の旧産炭地域などで横のつながりを模索する程度にとどまっている。また、十勝管内芽室町、更別村や後志管内喜茂別町などが、広報誌で合併問題についての特集を組み、さまざまな情報を提供しながら住民に問題提起する取り組みを始めた。議員や職員の定数削減、住民サービス低下の懸念、近隣自治体への配慮などから表立った議論さ 合併そのもののメリットは、突き詰めると合併によってそれまで以上に専門性のある職員を多く抱えられ、住民サービスの質を向上できることと、住民1人当たりの行政コストを抑制できることにある。行政コスト面からいえば最低でも人口5万人以上の規模が必要であり、職員の専門性の面からいえば職員を千人規模で抱えることのできる人口10万人以上が目安となる。 ■今求められている「生き残り策」しかし、1自治体当たりの平均面積が全国(約117平方キロメートル)の3倍以上もある北海道では、確かにスケールメリットは相殺されかねない。道庁がまとめた合併推進要綱の合併パターンの70%が総面積千平方キロメートルを超え、最大は2630平方キロメートルでいくつかの県の総面積を上回る。また、財政力指数で0.2前後の自治体がいくつくっつき合っても、「メリットはタカが知れている」という議論も必ずしも誤りではない。 だが、タカをくくっていられる状況にないことも現実である。「都市の論理に押し潰されかねない」という危機を感じるなら、どうしたら地方が生き残れるのか、合併なら可能なのか、合併しなくとも可能なのか、そこを突き詰めるときに来ている。市町村合併の道が困難であったり、いやであるのなら、「わがまちは合併なぞしなくとも、かく進む」という方向を明示すべきだろう。「ほかにうまい道が見つからない」なら合併に向けて腹をくくるべきだろう。 近隣自治体や国の模様を眺めながらの「横並び思考」は、住民にとって決して利益とはならない。合併はまちづくりの一つの選択枝に過ぎないが、合併論議はまちそのものの現在と未来を見つめ直す作業に他ならないのだから、今がそのチャンスともいえる。 ■「公共事業神話」は崩れ去る小泉内閣のタウンミーティングにおいても、改革論議の矛先が地方に向けられることに対する地方の不安と、不満が多く聞かれた。対話集会がときには「あれもこれも」の陳情集会となる場面もあり、鹿児島集会では、石原伸晃行革担当相が「必要なもの、いらないものをはっきり言わないと、『都市対地方』の構図になってしまう」と冷静な議論を求める一幕もあった。確かに、対立の果ては「田舎がいやなら都会に集まれ」ということになりかねないムードも広がりつつある。 タウンミーティングのライブ中継をインターネットで見ながら、「田舎のネズミと都会のネズミ」というイソップの寓話を連想した。「君らの暮らしは、アリと同じだね。僕の所にちょっと来てくれたまえ。なんでも思いのままだよ」。「アリ」と呼ばれたネズミは、都会を羨ましく思った-。あの話である。確かに「アリのまち」にだって、都市並みの下水道は欲しいし、高速道路もあれば便利だが、寓話の結末は、「麦をかじっていても、田舎暮らしをやっていきたいと思うんだよ」という田舎のネズミのネズミの言葉で終わる。イソップは都会と田舎の善し悪しではなく、その土地に住む者の生き方・選択を問いかけているのだと思う。地域のあり方・生き方を明確にできるまちにとって、小泉改革はチャンスでもあるのではないか。 ■痛み・ピンチはチャンスでもある 秋田県北部の二ツ井町では、計画中の下水道建設事業を断念し、町全域を合併処理浄化槽で整備することに方向転換した。公共下水道の対象人口は7千人で、下水道の場合、総事業費は約180億円で町支出金が約27億円。これに対し合併浄化槽の場合は、事業費約20億円で町支出が8億円で済む。建設時の接続のための負担金は、公共下水道が66万5千円に対 全国市町村の下水道事業は、旧建設省の公共下水が6割、残りは旧農水省の集落排水で進められている。下水管の敷設や処理場建設の約2分の1に国庫補助が付くが、残りは自治体の負担。多くは起債に頼り、返済や維持管理費は料金収入でまかなうのが原則となっているが、下水道会計の99%が収支赤字で、人口密度が低くなるほど割高な傾向にあるのが実情なのだ。 ■「身の丈」に合ったまちづくり
群馬県太田市の清水聖義市長は、95年の初登庁のその日、基礎のパイル打ちが始まろうかという段階の新庁舎建設工事に待ったをかけた。当然議会からは総攻撃を受けたが、結局、21階建て300億円の計画だった豪華庁舎は、12階建ての機能優先型の庁舎に取って代わり、建設費は半分に収まった。動き出したら途中で止まらないはずの「公共事業神話」もまた、物の見事に打ち砕かれた。そして、清水市長が粉々にしたのは、行政にはびこっていた既成概念そのものだった。 「助役を置かない条例」から広告入りの封筒まで、ときには一見無謀とも思える試みが、新しい道をかき分けていくのはなぜか。その秘密は、情報公開にある。太田市の行政審査会は市民6人で構成され、行政に関して知りたいことは何でもオープンにされる。隠す物がない裸の王様だからこそ、行政が住民、議会と真正面から向き合うことができる。これは「しなやか」というよりは「したたか」と呼ぶべきだろう。 二つのまちの試みは、地域主権型の地方自治の姿を示唆している。いわば「身の丈にあったまちづくり」が、分権時代のキーワードになるのではないだろうか。 ■エピローグお登勢が奉公した稲田家一族は明治3年(1870年)、淡路島を離れ日高の静内に集団入植した。新天地とはいえ、刀を鍬に代えての開墾作業は過酷で、誰もが故郷に逃げ帰りたい思いにかられた。史料には「百計多く蹉跌人心大いに沮喪」と記録されている。 挫折寸前の危機を乗り切り、新たな町づくりの気運を引き出したのは、稲田家の若き当主・邦植のリーダーシップだった。明治7年の支庁引継書には「邦植意を決して土着の実を示す。やがて自立の産に着き一区の富境と相成候、士族は自ら廉恥を知る、教ふれば北海道中の美風俗となるべし」とあり、開拓のモデルケースに取り上げられた。 「地域間競争」に吹き飛ばされる前に、「土着の実」と「自立の産」を目指した稲田魂にならいたい。 (了) (註:本稿は社団法人北海道開発問題研究調査会の機関誌「しゃりばり」2001年9月号に掲載した記事を補筆再録したものです) |
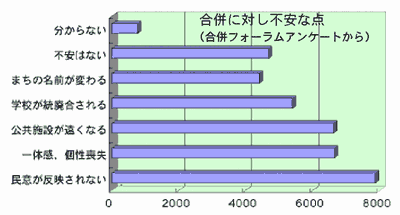 え避けようというムードがようやく打ち破られようとしているが、それにしても全体の動きは鈍重というほかない(グラフ参照)。
え避けようというムードがようやく打ち破られようとしているが、それにしても全体の動きは鈍重というほかない(グラフ参照)。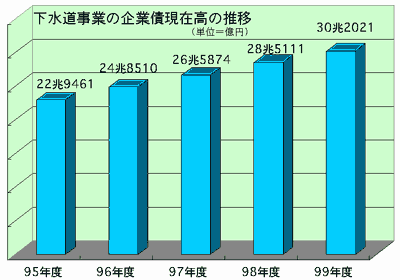 し、合併処理浄化槽(5〜10人用)の設置費が53万9千円。この試算に基づいて、公共下水道をやめ、その費用を合併処理浄化槽の補助に上乗せすることにしたのだ。
し、合併処理浄化槽(5〜10人用)の設置費が53万9千円。この試算に基づいて、公共下水道をやめ、その費用を合併処理浄化槽の補助に上乗せすることにしたのだ。 「公共下水道信仰」の打破は、住民の環境意識を高める効果ももたらした。住民総ぐるみによる国際的な環境基準ISO14001の取得や、木質系バイオマス技術を生かした新しい地域エネルギーの活用などにも目が向けられている。国の画一的な枠から飛び出し、地域の特性に合ったやり方や創意工夫と個性重視のまちづくりへとシフトしつつある。
「公共下水道信仰」の打破は、住民の環境意識を高める効果ももたらした。住民総ぐるみによる国際的な環境基準ISO14001の取得や、木質系バイオマス技術を生かした新しい地域エネルギーの活用などにも目が向けられている。国の画一的な枠から飛び出し、地域の特性に合ったやり方や創意工夫と個性重視のまちづくりへとシフトしつつある。