市町村合併を考える7-2 |
|
2001/3/26 |
総務省・新指針のカンどころ(2)議会の抵抗に、住民投票で対処新指針の第二のポイントは、住民投票制度を導入し、市町村合併に首長や議会が消極的でも、できるだけ民意を反映させようとしていることです。 合併に至る道筋は、有権者の50分の1以上の署名に基づく住民発議を経て法定の合併協議会が設置されるケースと、市町村や議会を中心にした任意の合併協議会から法定協議会に発展するケースとに大別されます。 ■55%の署名でも議会が否決 一般には住民発議が合併の原動力となりますが、実際には署名活動を通じて住民の合併に向けた機運が高まっても、首長、議会が壁となることが多くあります。これまで89件の住民発議がありましたが、協議会が設置されたのは、このうちわずか27%の24件 ■向こう1年に的絞り込む住民投票制度の導入は、首長、議会の壁を抑えることが狙いで、議会が合併協設置案を否決しても、首長判断か有権者の6分の1以上の署名があれば住民投票にかける道を開きました。住民投票で過半数が賛成すれば、議会の判断にかかわらず合併協を設置できるわけです。 住民投票制度の導入に対しては、全国市町村会や議長会が強く反発し、当初10分の1以上とされた住民請求の要件が6分の1に引き上げられた経緯があります。しかし、一方では住民発議の代表者の意見聴取を議会に義務付けたり、合併協設置後6か月以内に協議状況の公表を課すなど、首長や議会に対する圧力を強化しています。 新指針によれば、先の壱岐のケースでは、既に合併協が動き出し、年内に合併の可否の結論が出ることになります。都道府県の指導体制強化ととともに、向こう1年間が合併推進のヤマ場とする国の姿勢が見え隠れします。
|
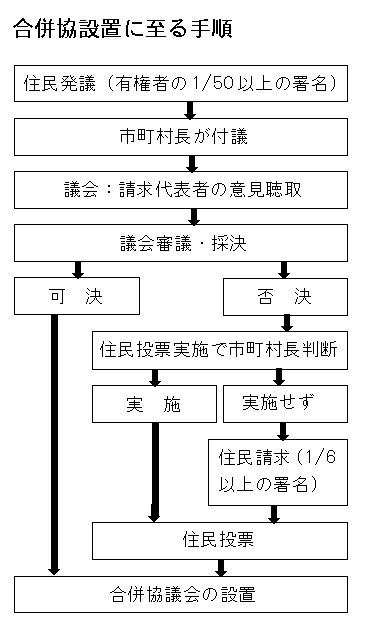 に過ぎません(2件は審議中)。「不発」に終わった63件の半数は、首長の段階で「門前払い」となり、残りは議会で否決されています。
最近の例では、香川県の観音寺市など10市町で住民発議が定数に達し、うち7市町で議会も合併協設置に同意したものの、3町の議会が否決し、白紙に戻ってしまいました。否決3町の署名が有権者の8〜12%で、全体の19.5%を大きく下回ったことが「機熟せず」との判断の背景となりました。
署名率が一つの目安となっているわけですが、長崎県壱岐の島4町の合併構想では、55.1%の署名率にもかかわらず石田町議会が合併協設置を否決しました。町の財政状況が必ずしも他に比べて厳しいわけではないことや、独自性を重視する意見が大勢を占めたためですが、議会と住民意思の「ねじれ現象」が際立った出来事でした。
に過ぎません(2件は審議中)。「不発」に終わった63件の半数は、首長の段階で「門前払い」となり、残りは議会で否決されています。
最近の例では、香川県の観音寺市など10市町で住民発議が定数に達し、うち7市町で議会も合併協設置に同意したものの、3町の議会が否決し、白紙に戻ってしまいました。否決3町の署名が有権者の8〜12%で、全体の19.5%を大きく下回ったことが「機熟せず」との判断の背景となりました。
署名率が一つの目安となっているわけですが、長崎県壱岐の島4町の合併構想では、55.1%の署名率にもかかわらず石田町議会が合併協設置を否決しました。町の財政状況が必ずしも他に比べて厳しいわけではないことや、独自性を重視する意見が大勢を占めたためですが、議会と住民意思の「ねじれ現象」が際立った出来事でした。