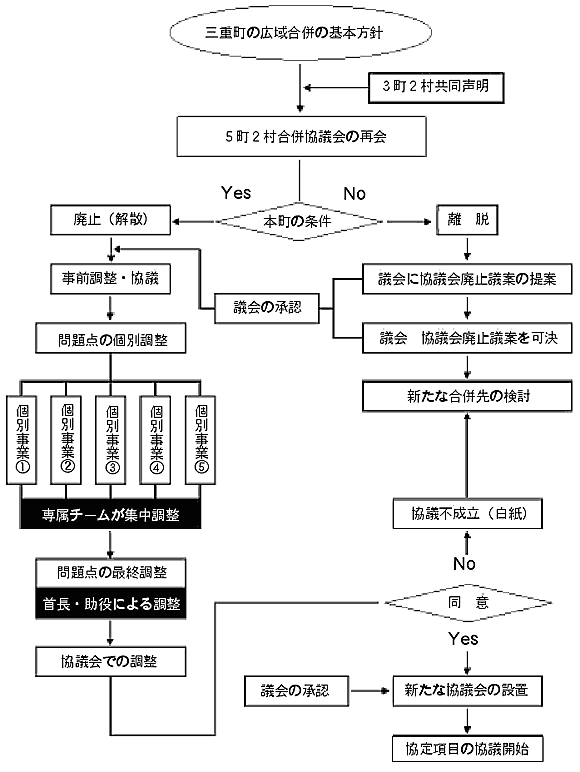|
||
<1>高知県越知町〜合併前提・採決強行に反発高知県中部の池川、佐川、越知(おち)3町と吾川、仁淀2村は、2002年10月に法定の高吾北地域合併協議会を設置、2005年2月の合併・市政移行に向けて、議論を進めてきました。ところが、2003年5月の第6回協議会の途中で越知町の全委員が退席する事態が起きました。 ■「単独自立」方針を町議会も支持
議会で吉岡町長は、協議会の議論が合併を大前提とした流れとなっており、越知町と他の4町村との間に意識のギャップがあることを挙げました。また、7月29日の協議会では、離脱の理由として(1)本庁・支所機能をめぐる協議会の議論に疑義がある(2)新市の名称公募が始まると合併が既定路線化しかねない〜と説明しました。 本庁・支所問題をめぐっては、5月の協議会で現佐川町役場を本庁とする提案に対し、越知町が住民に説明するための猶予を求めました。しかし「庁舎位置が決まらなければ住民の判断材料にならない」とする意見に押し切られる格好となり、採決を前に越知町の全委員が退場してしまいました。結局、残された委員の全員賛成で佐川本庁案が採択されたわけです。
■役場維持に期待感、離脱で「飛び地」化 庁舎論議の過程を見ると、越知町は「総合支所」の位置付けで基本的に現在の役場機能が維持されることに期待を寄せていました。町民の中にも、全人口の半数を抱える佐川町に本庁が置かれ、「支所」に縮小されることに対し不安の声が聞かれました。 5町村のほぼ中央に位置し、広域行政の拠点も置かれている「地の利」を合併後も生かしたいと考える越知町に対して、吾川、仁淀村などは佐川町が中心となることにそう違和感がない。しかし、越知町が抜けた新市の「いびつ」さに当惑しているのが実情のようです。また、越知町の「単独自立」は内容がやや不透明で、合併協議の在り方とともに課題を残しました。 <2>大分県三重町〜「理念共有」前提の合併望む任意合併協議会のテーブルに一旦着いた大分県大野郡の6町2村のうち野津町は2003年3月、離脱して大分市との法定協に参加。残る5町2村も、2005年3月の合併を目指して法定協を設置しました。 ■財政情報公開で意識差
(1)財政状況の好評に対する考え方など合併に対する基本的な考えにギャップがある (2)法定協設置後に朝地、犬飼町が住民投票を行い、大分市との合併を求める犬飼町民と議会の間にねじれが生じ、実質的な協議が進まない (3)地域づくりの理念を共有できる自治体との広域合併を目指していきたい 特に、芦刈・三重町長が重視したのは、「情報公開と住民参加」の視点から財政状況を全面開示することでした。これに対し、公表する内容やタイミングなどをめぐって異論も出され、協議会の結論が先延ばしになったことが、芦刈町長が「意識ギャップ」を感じる要因となったことがうかがえます。 ■「駆け込み事業」を懸念 7町村の財政状況をみると、財政の硬直化を表す経常収支比率は、7町村とも警戒ラインの90%前後のレベルにあります。住民1人当たりの地方債残高も全体に高水準にあります。 このため、芦刈町長は、財政の透明化と併せて、合併前段での各自治体の健全化の取り組みを強く主張しています。また、合併後に旧町村間の公平を欠いたり、基金の急激な取り崩し・多額の起債を要するような「駆け込み事業」に歯止めをかけることも求めていました。 実際に駆け込み的な動きがあったかどうかは明かではないものの、財政情報の共有が図れなかったことが、不信感を増幅させる背景ともなったようです。
<3>合併何のため〜目標は明確か
■課題を具体化し、集中的に協議 三重町の場合は、少なくとも町長が合併後の姿をビジョンとして描き、「理念の共有」と「情報公開・住民参加」の手法を明確にしている点で、評価できるでしょう。また、形式的な議論よりも具体的な問題・課題に重点を置いた議論を優先する方法も参考になりそうです。
フローチャートにあるように、個別のテーマについて専門チームを組んで集中的に協議(事前調整)することで、共通理解を深めていく手法です。大野郡における具体的課題としては、将来の財政運営に大きな影響を及ぼすことが予想される町立病院やCATV、公共下水道、道の駅事業などを挙げてます。「健全化を図る」といった通り一遍の対応策ではなく、民営化やPFIの活用など、より具体的な方策を打ち出そうというわけです。 ■「役所の合併」に落とし穴 そうした意味では、本来、任意協議会の段階で問題・課題を出し合い、克服・解決の知恵を寄せ集めることが重要なのでしょう。逆に、特例措置を期待し、タイムリミットに追い立てられての協議には、落とし穴も潜んでいます。高知県・高吾北地域合併協の例でみると、規定に従い定足数も満たしているとはいえ、1町の委員全員が不在状態での採決は、やはり異常です。 思惑通りに進まないから離脱というのであれば、それも問題ですが、何のための合併か、誰のための合併かという原点に立ち返れば、解決の道は自ずから見えてくるはずです。 「役所同士の合併」ということであれば、問題はまた別なのですが。 |
||
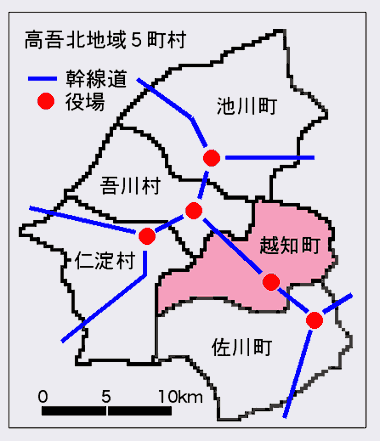 吉岡珍正・越知町長は、6月25日の町議会特別委で協議会離脱と単独自立を目指す考えを示し、議会側も賛成8反対5で離脱方針を承認しました。越知町は、区域のほぼ中央に位置することもあって、残る4町村は、今後の対応に苦慮しています。
吉岡珍正・越知町長は、6月25日の町議会特別委で協議会離脱と単独自立を目指す考えを示し、議会側も賛成8反対5で離脱方針を承認しました。越知町は、区域のほぼ中央に位置することもあって、残る4町村は、今後の対応に苦慮しています。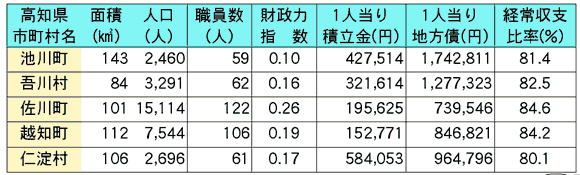
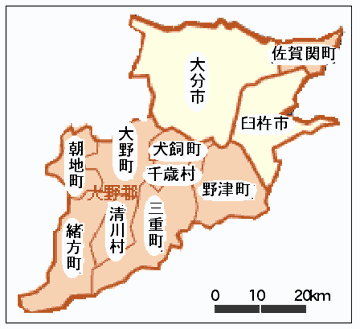 ところが、中核的な存在の三重町は、7月4日の協議会で、協議会を廃止した上で新たな広域合併協議に取り組むことを提案しました。これに対し、ほかの5町村は現在の枠組みの維持を主張し、結局、三重町は法定協離脱を表明しました。三重町の離脱表明は唐突にも見えましたが、芦刈幸雄町長は次のような離脱の理由を挙げました。
ところが、中核的な存在の三重町は、7月4日の協議会で、協議会を廃止した上で新たな広域合併協議に取り組むことを提案しました。これに対し、ほかの5町村は現在の枠組みの維持を主張し、結局、三重町は法定協離脱を表明しました。三重町の離脱表明は唐突にも見えましたが、芦刈幸雄町長は次のような離脱の理由を挙げました。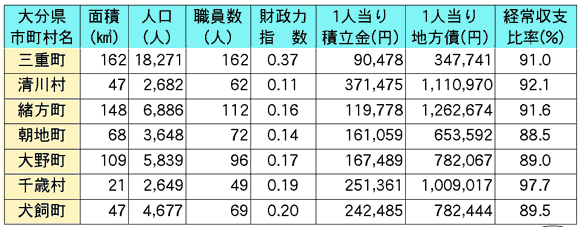
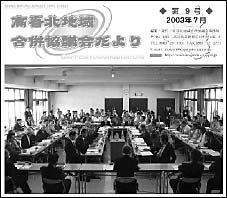 大分県三重町の法定合併協離脱は、他の自治体にとっては唐突と映り、合併特例法の2005年3月という期限を考えると、大きな時間的ロストも見えます。しかし、同床異夢を抱えたまま合併に雪崩を打ったり、損得論の末に協議が破綻する現実の一面を踏まえると、立ち止まって考えたり、遠回りすることも大事かと思えます。
大分県三重町の法定合併協離脱は、他の自治体にとっては唐突と映り、合併特例法の2005年3月という期限を考えると、大きな時間的ロストも見えます。しかし、同床異夢を抱えたまま合併に雪崩を打ったり、損得論の末に協議が破綻する現実の一面を踏まえると、立ち止まって考えたり、遠回りすることも大事かと思えます。